仕事をやりたくないと思ってはいけないという誤解
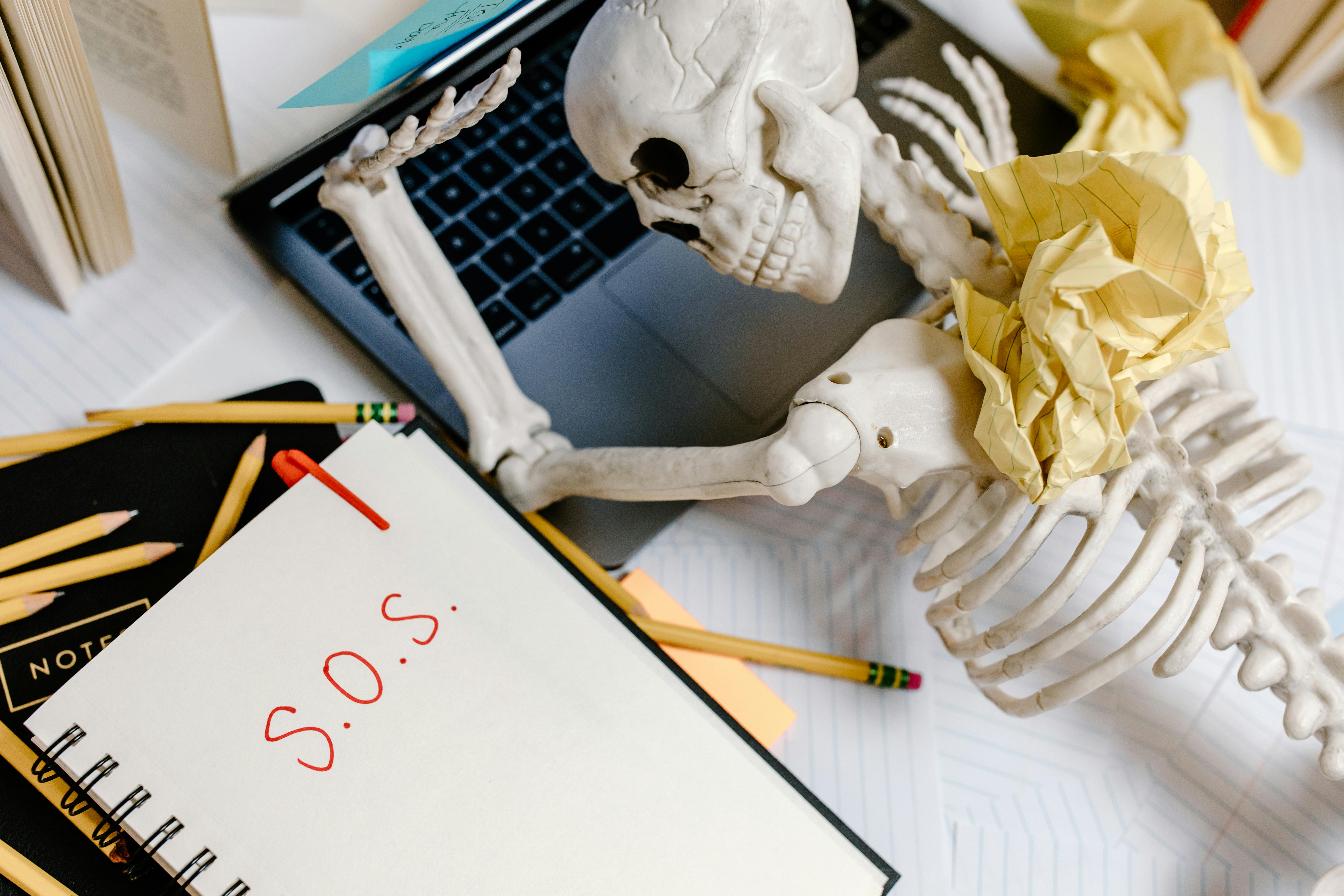
はじめに
「仕事をやりたくないなんて言ってはいけない」
これは多くの社会人にとって、ほとんど反射的に受け入れてしまっている前提です。
実際、会社員として雇われ、給与を受け取る以上、与えられた仕事を遂行する責任があります。気分が乗らないからといって「やりたくない」と公言することは、職場の秩序を乱し、周囲に迷惑をかける可能性もあるでしょう。
しかし、この「言ってはいけない」という刷り込みが強すぎるがゆえに、多くの人が本当に危うい落とし穴に陥ってしまいます。
それは、「やりたくない」という感情そのものを見ないようにして、心の声に耳を塞いでしまうことです。
問題は「やりたくない」と思うことそのものではありません。むしろ、その感情を無視し続けることの方が、キャリアを歪め、人生全体に大きな影響を及ぼします。
本記事では、なぜ「やりたくない」という感情を丁寧に見つめることが大切なのか、その思考プロセスがどのようにキャリア形成に不可欠なのか、掘り下げて解説します
1. 「やりたくない」と思うのは自然なこと
1-1. 人間は常に欲求と葛藤する存在
どんなに優秀なビジネスパーソンであっても、全ての仕事が「やりたいこと」になるわけではありません。むしろ、「やりたくない」と感じる瞬間は誰にでもあります。人間には本能的に「楽をしたい」「快を求めたい」という欲求があるため、義務や責任と直面すれば葛藤が生じるのは当然です。
1-2. 「やりたくない」=怠惰ではない
日本の職場文化では、「やりたくない」という言葉はしばしば「怠け者」「甘え」と同義に扱われがちです。しかし実際には、これは短絡的なレッテル貼りです。
やりたくない感情の背景には、例えば以下のような要因が潜んでいます。
• 能力のミスマッチ(自分の強みを活かせない)
• 価値観の不一致(やる意味を感じられない)
• 成長の停滞(単調で学びがない)
• 環境の問題(人間関係や制度に不満がある)
つまり「やりたくない」は単なる怠惰の表れではなく、キャリアの方向性を見直すサインなのです
2. 「やりたくない」に蓋をする危険性
2-1. ストレスの蓄積と心身への悪影響
やりたくない感情を無視し続ければ、心は消耗し、体にも不調が現れます。慢性的なストレスはモチベーション低下だけでなく、うつ病など深刻な問題につながりかねません。
2-2. キャリアの偶然依存
「やりたくない」と感じる原因を分析せずに仕事を続ければ、自分に合うキャリアを自分で選ぶことができなくなります。結果として、次の職場でも同じ不満を繰り返し、偶然「合う」仕事に出会うのを待つしかなくなります。これはキャリア形成の再現性を著しく損なう行為です。
2-3. 無自覚の惰性キャリア
やりたくない感情に気づかないまま進んでしまうと、気づけば「無難に居続ける」だけのキャリアになってしまいます。本人も大きな充実感を得られず、組織にとっても活躍しない存在になってしまうのです。
3. 「やりたくない」という感情の効用
3-1. 自己理解を深めるコンパス
「やりたくない」と感じるとき、その背景には「自分が大事にしていることか」が隠れています。たとえば、
• 人と関わるのが好きな人が、延々と一人で資料作成をやらされれば「やりたくない」と感じる。
• 新しい挑戦を好む人が、何年も同じルーティンを繰り返せば「やりたくない」と思う。
このように、「やりたくない」という感情は、自分の価値観や適性を映し出す鏡なのです。
3-2. キャリア選択の判断材料
「やりたくない」という感情を分析することで、転職すべきか、職場に留まって工夫すべきかが見えてきます。単なる逃避か、それとも環境を変えるべき必然なのかを判断するうえで、最も重要な材料になります。
3-3. 成長のきっかけ
やりたくない理由を探っていくと、「実はスキル不足で不安」「成果を出せる自信がない」などの内面的な課題が見えてくることもあります。そうした課題に向き合い克服することで、結果的に自分を大きく成長させることができます。
4. 実践すべき思考プロセス
では具体的に、「やりたくない」という感情にどう向き合えばよいのでしょうか。以下のプロセスが有効です。
4-1. 感情を認める
まずは「やりたくない」と感じている自分を否定せず、そのまま受け止めること。ここで「自分は怠けている」と自己嫌悪に陥る必要はありません。
4-2. 原因を掘り下げる
「なぜやりたくないのか」を分解します。
• スキルが足りない → 学習で解決可能か?
• 仕事内容が合わない → 部署異動や転職で改善可能か?
• 人間関係の問題 → コミュニケーションで乗り越えられるか?
4-3. 意義を再定義する
やりたくない仕事でも、その中に「学べること」「将来につながる要素」がないかを探します。たとえば、苦手な作業も「忍耐力を鍛える」「基礎を固める」機会と捉え直すことができます。
4-4. 行動を選択する
分析の結果に基づき、具体的な行動を決めます。
• 今の職場で工夫して取り組む
• 上司に相談して役割を調整する
• 転職活動を開始する
大事なのは、「やりたくない」という感情から目を逸らさず、行動につなげることです。
5. 転職するにしても留まるにしても不可欠なこと
ここで強調したいのは、転職するにしても留まるにしても、この思考プロセスは必ず必要になるという点です。
以下、その理由を説明します。
5-1. 留まる場合
やりたくない感情を分析し、工夫して仕事を再定義できれば、同じ職場・同じ仕事でも充実感を得られるようになります。これは組織にとっても本人にとっても大きなプラスです。
5-2. 転職する場合
やりたくない理由を言語化できていなければ、転職先でも同じ不満を繰り返す可能性が高いです。逆に、分析を経て「自分は◯◯を大切にしたい」と明確に分かっていれば、転職先選びの基準が定まり、再現性あるキャリア形成につながります。
6. まとめ 〜「やりたくない」はキャリアを開く扉〜
「仕事をやりたくないと言ってはいけない」というのは、大きな誤解です。
もちろん社会人としての責任を放棄してよいわけではありません。しかし、「やりたくない」という感情を抑え込むのではなく、丁寧に見つめ、自分との対話を深めることこそが、より良いキャリアへの扉を開くのです。
• やりたくない感情は怠惰ではなく、自己理解のきっかけ
• 蓋をするとストレス・惰性キャリア・偶然依存を招く
• 分析すれば、成長や転職判断の羅針盤になる
• 留まるにしても転職するにしても、気持ちを丁寧に見つめ言語化するプロセスは不可欠
やりたくない気持ちに蓋をせず、自分の声を聞くことから始めてみてください。
その小さな一歩が、必ずあなたのキャリアの軸をつくっていきます。
理想の転職を目指すなら
コンサル業界への転職やキャリアアップを目指す場合、エージェント選定も重要な要素の一つです。
未経験者のコンサル転職や、コンサル出身者の経営幹部転職特化など明確な強みがあり、選考対策からキャリア設計まで手厚いサポートがあるエージェントをおすすめしています。
現状に不満や将来に不安がある方は、先ずは以下サイトへの無料登録と無料相談から始めてみるなど、具体的な行動からキャリアプランを探してみてはいかがでしょうか。






