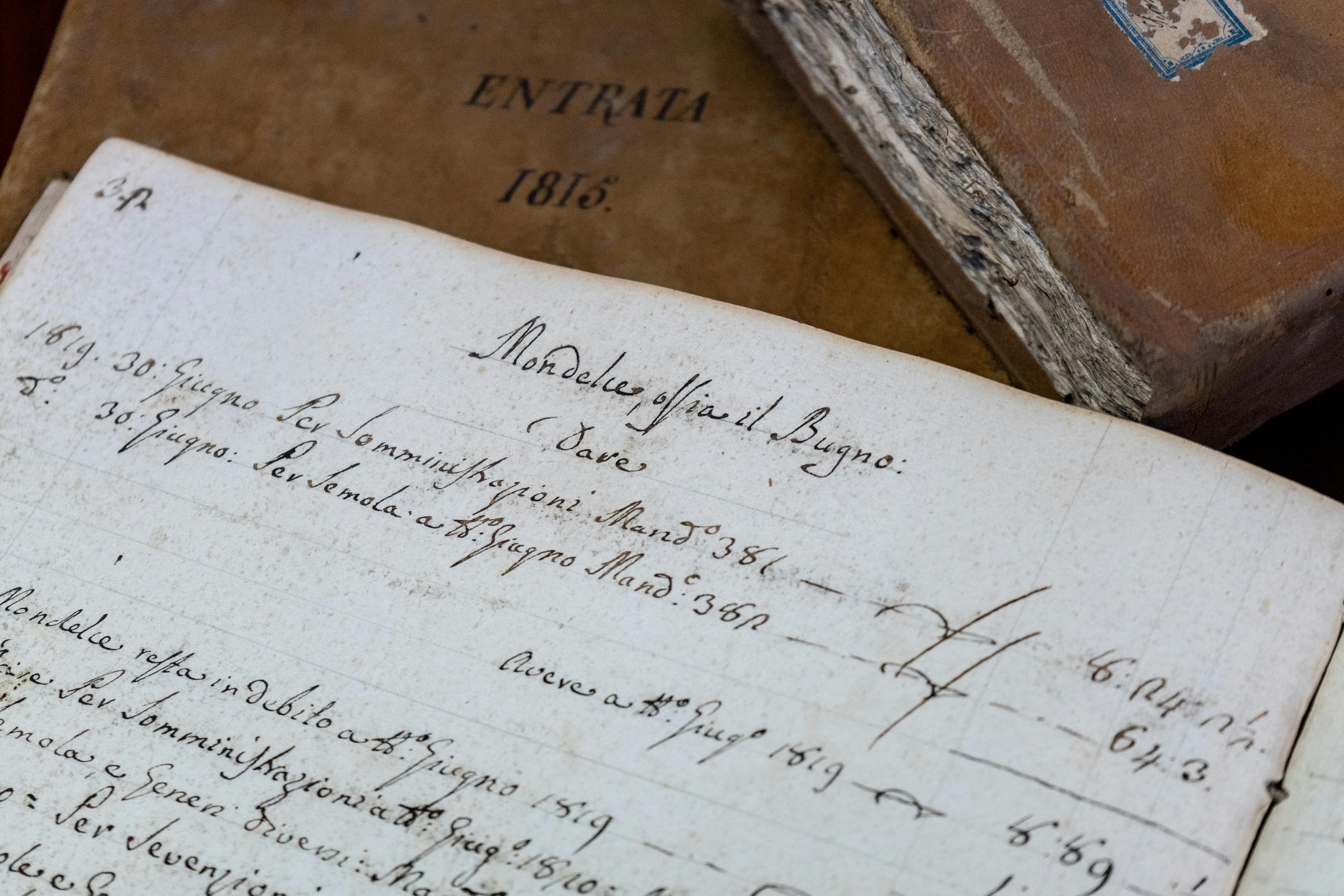潰しが効く汎用的なスキルが無い中でどうキャリアを築くべきか

はじめに
現代のキャリア論では、「市場価値を高める」「どこでも通用するスキルを身につけよう」といったフレーズが繰り返し語られます。SNSやキャリア本、転職エージェントの広告などでも、「汎用的なスキルを得れば潰しが効く」「どの会社でも生きていける」といったメッセージを目にしたことがある人は多いでしょう。
しかし、冷静に考えてみれば、この「どこでも潰しが効くスキル」とは何なのか、具体的に答えられる人はほとんどいません。Excel操作?プレゼン能力?論理的思考?英語? いずれも一定の有効性はありますが、それだけでキャリアが保証されることはありません。
実際には、多くの社会人にとって「どこでも潰しが効く汎用的なスキル」など存在しないのです。それにもかかわらず、その幻想を追いかけ続ける人が、無駄な転職を繰り返し、結果としてキャリアを停滞させてしまうケースが少なくありません。
本記事では、なぜ汎用スキルという幻想が広まったのか、実際にはどのようなスキルが評価されるのか、そして社会人がどうキャリアを捉え直すべきかを、現実的に考えていきたいと思います。
汎用的なスキルという幻想が広がった背景
1. 転職市場の広告戦略
転職エージェントや求人広告は、当然ながら「人が動くこと」で利益を得ています。したがって、人々を「現状に不安を抱かせる」ことが第一歩になるわけです。
そのとき使いやすいキーワードが「市場価値」と「汎用性」です。
- 「あなたの今のスキルは、他社でも通用しますか?」
- 「一社専属の経験だけではリスクです」
- 「どこでも潰しが効くスキルを磨きましょう」
こうした言葉は、安易に転職を考えるきっかけを作ります。しかしそれはキャリアの実態を反映しているというより、あくまで人材ビジネスの論理です。
2. ビジネス書やSNSのシンプルな言説
もう一つの要因は、自己啓発的なキャリア論がシンプルさを重視するためです。難しい話をしても人に響かないので、「どこでも通用するスキルを持てば安心」という単純化された物語が好まれて広がります。
しかし現実はもっと複雑です。ある会社で通用するスキルが、業界や文化が異なればほとんど意味をなさないことも珍しくありません。
3. 「専門性」への漠然とした恐怖
専門性を持たなければならないという意識がある一方で、特定分野に閉じ込められる不安もあります。「もっと汎用性があるスキルなら、逃げ場がある」と信じたい心理が、人を幻想へと導くのです。
現実:スキルは環境依存でしか評価されない
1. スキルの価値は「文脈」で決まる
例えば、英語ができるというスキルを考えてみましょう。グローバル企業で海外拠点とのやり取りが日常的に発生する環境では高く評価されるでしょう。しかし、国内中心の中小企業で英語を使う場がほとんどなければ、その価値は一気に下がります。
つまり、どれだけ「汎用的」に見えるスキルであっても、評価されるかどうかは環境に依存するのです。
2. 「論理的思考力」も万能ではない
よく言われる「ロジカルシンキング」も同様です。確かに重要な能力ですが、それだけで成果が出るわけではありません。現場では「人を動かす力」「泥臭い調整力」「現実的に落とし込む力」など、論理以外の要素が不可欠です。
論理的であることは土台にはなりますが、それ自体が「どこでも通用する万能スキル」とは言えません。
3. スキルは「組み合わせ」と「適用範囲」で生きる
結局のところ、スキルの価値は単体で成立するのではなく、「その人の業務経験」「業界知識」「人間関係構築力」といった要素との組み合わせで評価されます。
つまり、スキルはそれ自体で独立した「武器」ではなく、環境の中で活かされる「道具」に過ぎないのです。
「潰しが効く」と信じて転職を繰り返すリスク
1. ジョブホッパーの印象
転職回数が多い人は、それだけで「この人は腰が落ち着かないのでは」と見られるリスクがあります。本人は「汎用スキルを磨くため」と言うかもしれませんが、採用側からすれば「成果が出ずに辞めているのでは」と疑われがちです。
2. 蓄積されない経験
転職を繰り返すと、各職場で中途半端にスキルを学んだまま終わってしまいます。どの分野でも浅い経験しか持たないため、結局「専門性のない人」になってしまうのです。
3. 本当の意味での市場価値は下がる
短期的に「経験社数は多い」「スキルセットは広い」と見えるかもしれません。しかし長期的には「強みが曖昧な人」と見られ、むしろ市場価値が下がってしまうのが現実です。
実際に評価されるものとは何か
1. 再現性のある成果
どの業界でも最も評価されるのは「成果を出した経験」です。営業であれば売上実績、企画であればプロジェクトの成功、エンジニアであればシステムの安定稼働。これらは環境が変わっても一定の説得力を持ちます。
2. 「文脈を理解する力」
実務の世界では、どんなにスキルがあっても「その会社・その業界の前提」を理解できなければ役に立ちません。だからこそ、新しい環境に素早く適応し、文脈を読み取り、自分の強みを当てはめられる人が評価されます。
3. 人間関係構築力
どの組織でも、結局は人が成果を動かします。信頼を築き、周囲を巻き込み、協力を得られる力は、どんな職場でも高い価値を持ちます。
「汎用スキル」ではなく「自分の軸」を見つける
1. 「どこでも」ではなく「どこかで」強い人になる
「どこでも通用する人」を目指すのではなく、「ある領域では確実に強い人」を目指す方がはるかに現実的です。その強みが結果的に他の場でも応用できることはありますが、それは副次的な効果にすぎません。
2. 比較優位を探す
絶対的な強さではなくても、自分なりに「他の人よりはできる」「自然と人より時間をかけられる」ことが必ずあります。それを徹底的に伸ばすことで、自分の居場所が見えてきます。
個人的には、後者の「他の人よりも時間をかけられる領域」や「他の人よりも時間をかけた経験」を重要視することをおすすめします。
なぜなら、基本的にかけた時間に比例する形で能力が向上しそれが自分の軸となる為です。
3. キャリアは「積み上げ」でしか形にならない
スキルも実績も、時間をかけて積み上げるからこそ説得力を持ちます。目先の「潰しが効く幻想」に飛びつくより、一つひとつの経験を重ねる方が、長期的には確実に強いキャリアを築けます。
結論:幻想に振り回されないキャリアを
「どこでも潰しが効く汎用スキル」を追いかけても、実際にはそんな万能スキルは存在しません。スキルは文脈依存であり、価値は環境によって大きく変わります。
本当に大切なのは、
- 自分が成果を出せる領域を知ること
- その経験を積み重ねていくこと
- 新しい環境に適応する力を養うこと
この三つです。
転職を繰り返すこと自体が悪いわけではありません。しかし「汎用スキルさえあればどこでも生きていける」という幻想に振り回されての転職は、あなたのキャリアをむしろ弱くしてしまう危険があります。
今いる環境での経験をどう積み上げるか。自分の中の比較優位をどう育てるか。そこにこそ、長期的にキャリアを豊かにする道があります。
理想の転職を目指すなら
コンサル業界への転職やキャリアアップを目指す場合、エージェント選定も重要な要素の一つです。
未経験者のコンサル転職や、コンサル出身者の経営幹部転職特化など明確な強みがあり、選考対策からキャリア設計まで手厚いサポートがあるエージェントをおすすめしています。
現状に不満や将来に不安がある方は、先ずは以下サイトへの無料登録と無料相談から始めてみるなど、具体的な行動からキャリアプランを探してみてはいかがでしょうか。