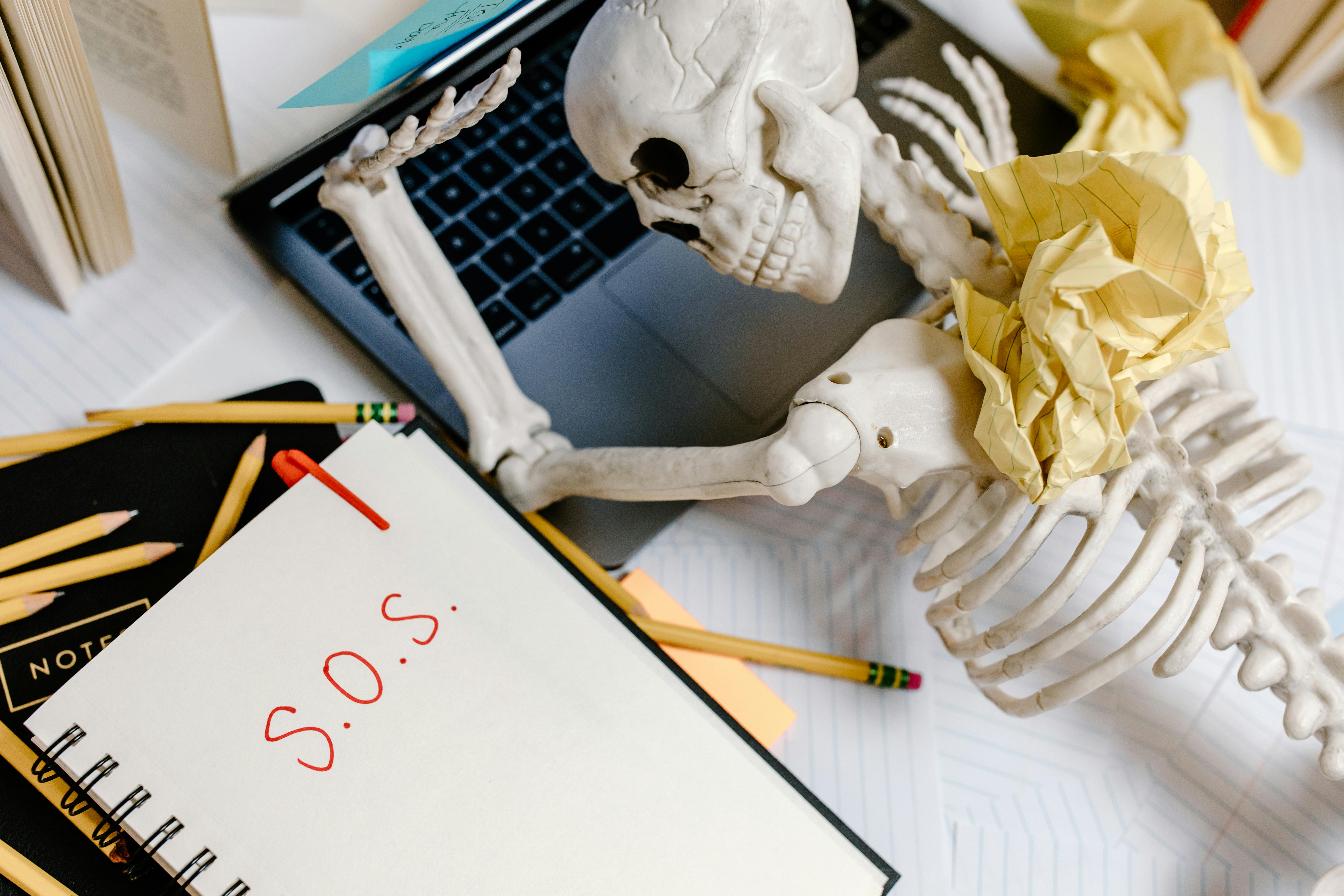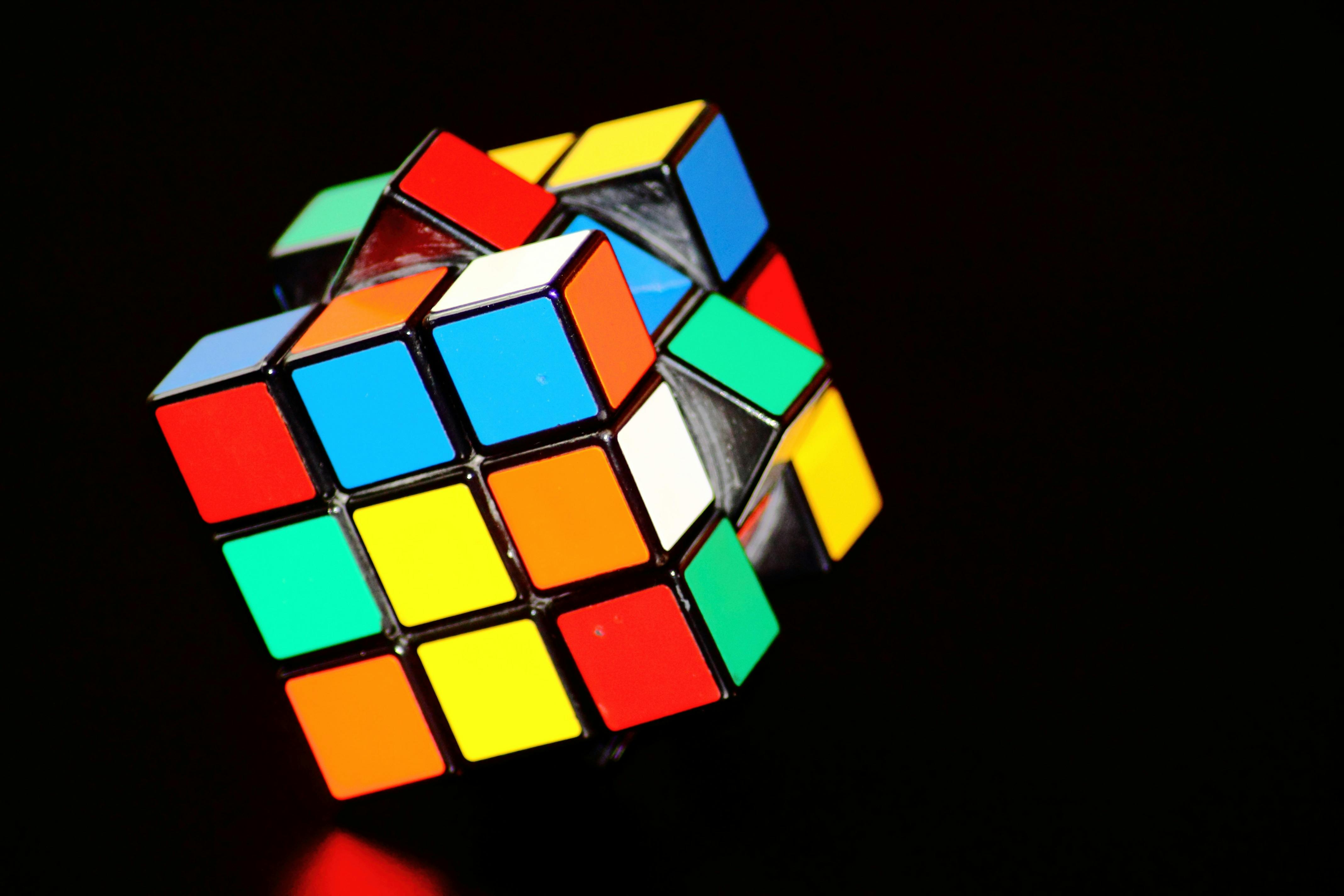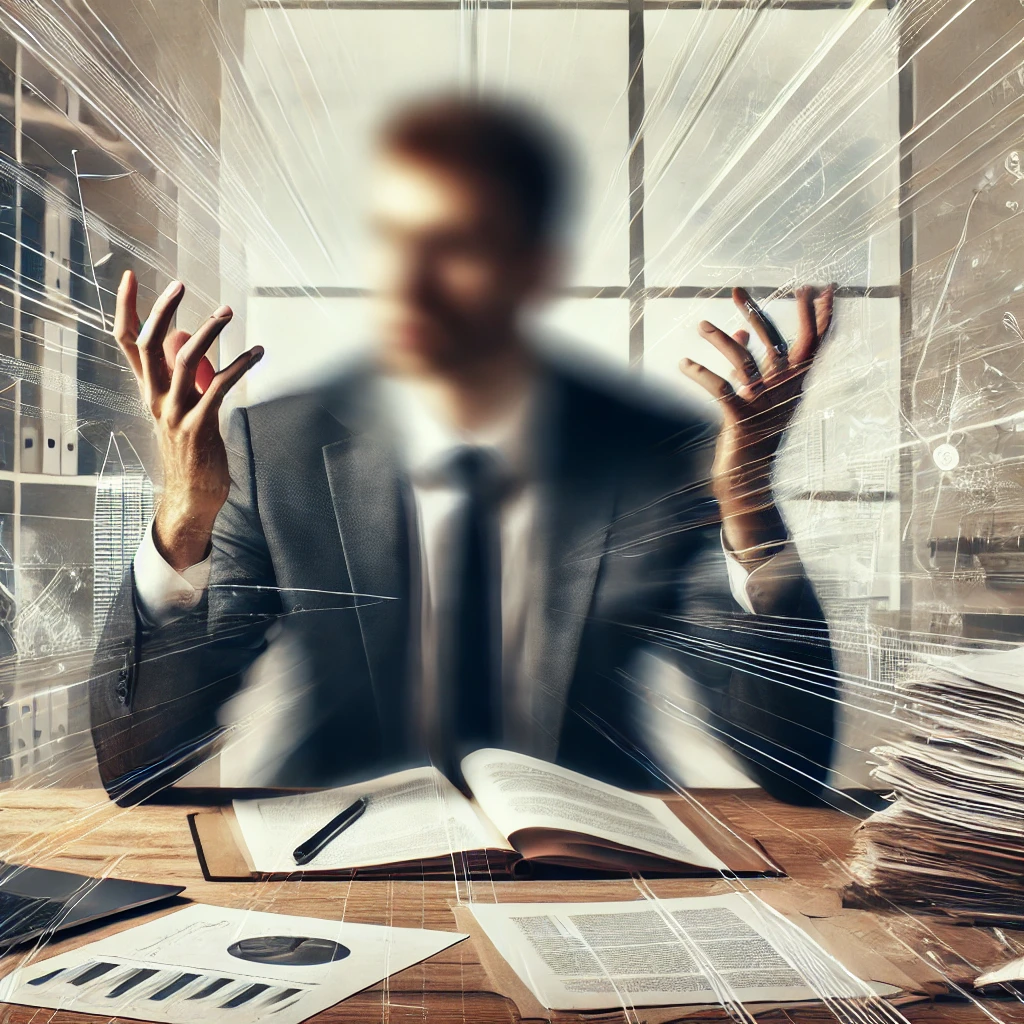平等な社会・公平な評価が残酷である理由

はじめに
私たちは子どもの頃から「平等は良いこと」「公平であることが望ましい」と教わってきました。学校教育においても、努力すれば報われる、頑張った人は正しく評価される、という理想が語られます。社会に出ても「透明な評価制度」「成果主義」「公平な社会」といった言葉はポジティブに使われます。
しかし現実に立ち返ると、「平等で公平な評価」が必ずしも心地よいものではないことに気づきます。むしろ、非常に残酷な側面を持っています。なぜなら、平等で公平であるということは、裏を返せば 誰のせいにもできず、すべてが自己責任になるということだからです。
本稿では、平等や公平がなぜ残酷たりえるのかを考え、同時に、それでも私たちがどう向き合うべきかを掘り下げていきます。
「平等で公平」とは何を意味するのか
まずは定義から整理しましょう。
- 平等:すべての人が同じ条件で扱われること。
- 公平:その人の努力や成果に応じて正しく評価されること。
この二つは似ているようで微妙に違います。平等は「機会やルールの一律化」を指し、公平は「成果に対する適切な評価」を意味します。
現代社会では「機会の平等」と「成果に対する公平な評価」が同時に求められる傾向があります。つまり「出発点は同じにしよう」「その上で結果は努力や能力に応じて決まるべきだ」という考え方です。
理論上はとても美しい仕組みです。しかし、いざ現実に適用すると、そこには大きな落とし穴があります。
平等・公平が残酷である理由
1. 言い訳ができない
平等で公平な評価制度では、評価者の好き嫌い、人脈、運、不透明な外部要因に頼る余地がなくなります。すべてが「実力」と「成果」によって決まるからです。
そうなると、成果が出なかったときに「上司が見る目がなかった」「あの部署に配属されたから運が悪かった」といった言い訳ができません。逃げ場がなくなるのです。
言い換えれば、評価の矛先が常に自分に突き刺さる状態となり、これは時に非常にしんどい感情を引き起こします。
2. 一握りの人しか生き残れない
どんな環境でも成果を出せる「本当の実力者」は存在します。彼らにとっては公平な評価はむしろ好都合です。なぜなら環境や上司の好き嫌いに左右されず、常に自分の力で勝ち残れるからです。
しかし、世の中の大多数は凡人です。どんなに努力しても結果が出ないときがあるし、体調や環境に左右されることもある。凡人にとって「完全に平等で公平な社会」は逃げ道のない過酷な舞台です。
3. 守られていた不公平もなくなる
意外に思うかもしれませんが、私たちは「不公平さ」によって守られている部分もあります。
- 上司がたまたま自分を気に入ってくれて高く評価してくれた。
- プロジェクトがたまたま追い風を受けて成果を出せた。
- 会社の仕組みが曖昧で、能力不足が露呈せずに済んだ。
こうした「不公平な恩恵」によって救われている人は少なくありません。公平が徹底されると、それらが一切なくなり、自分の力不足が赤裸々にさらされてしまいます。
不公平や不透明さが「救い」になる場合
ここで一歩踏み込んで考えてみましょう。多くの人は「評価は公平であるべきだ」と口にします。しかし一方で、実際には不公平や不透明な評価に守られている側面があるのです。
たとえば会社の評価制度では、成果だけでなくプロセスや努力が加点されることがあります。これは一見「不公平」に見えるかもしれませんが、努力がすぐに結果に結びつかない人にとっては救済措置になります。
あるいは、評価者の好き嫌いに助けられるケースもあります。能力的に少し劣っていても、誠実さや人柄を評価されて高い評価を得ることもある。これも純粋な成果主義から見れば不公平ですが、社会を柔らかくしている側面でもあります。
要するに、 不公平さは人を救うクッションの役割を果たすことがある のです。
自己責任の社会のメリット
では、すべてが自己責任になる「公平な評価」には良いところがないのでしょうか。決してそうではありません。自己責任の社会には次のような利点があります。
1. 改善の余地は常に自分にある
「自分のせいである」と認識することは辛い反面、「だから自分で改善できる」という意味でもあります。もし外部要因や他人のせいにしてしまうと、改善の余地がなくなります。
自責思考は苦しいですが、唯一「自分を変えられる可能性」を持った思考でもあるのです。
2. 痛みを通じた学びが深い
誰かに守られている限り、人は本気で学びません。自分が痛い目に遭ったときこそ、改善への意識が強く芽生えます。失敗体験が骨身に染みるからこそ、次に同じ過ちを繰り返さない。
公平な評価は、この「痛みを通じた学び」を個人に突きつける仕組みとも言えます。
3. 他人のせいにせず、自分の成長に集中できる
不公平な仕組みがあると、人は不平不満に時間を費やします。「あの人は上司に好かれているから得をしている」「私は運が悪かっただけだ」と言い訳を探し続けます。
一方で公平な仕組みの中では、不満を言う余地がなくなるので、嫌でも自分の行動や能力に目を向けるようになります。これは長期的に見れば成長につながります。
どう向き合うべきか:自責とセルフケアのバランス
公平な評価の下では、自責思考が求められます。しかし、自責を突き詰めすぎるとメンタルを壊します。ここにバランス感覚が必要です。
1. 自責思考を「改善のための道具」として使う
「すべて自分のせいだ」と自分を責め続けるのは危険です。そうではなく、「自分に改善の余地はなかったか?」と建設的に問うためのツールとして自責を使うのです。
2. メンタルのケアを優先する
結果が出なくても、自己否定に陥らないこと。むしろ「今回はダメだったけど、次に活かせる学びがあった」と切り替えること。公平な評価の世界では、このセルフケア能力が極めて重要になります。
3. 不公平も受け入れる
矛盾するようですが、「不公平さに救われている部分もある」と認識しておくことも大切です。人は誰しも完全な実力者ではなく、環境や他人の好意に支えられている部分がある。だからこそ、すべてを背負い込みすぎない柔らかさも必要です。
結論:公平さは刃物のようなもの
平等で公平な評価は、美しくもあり、残酷でもあります。それはちょうど鋭利な刃物のようなものです。うまく使えば自分を成長させ、キャリアを磨く道具になります。しかし扱いを誤れば、自分自身を深く傷つけてしまうリスクもあります。
だからこそ、私は常に以下を意識することを習慣としています。
- 公平な評価に逃げ場がないのは事実。だからこそ改善の余地を探す。
- 不公平さに救われていることを忘れない。
- 自責思考は持ちつつも、メンタルの健康を第一にする。
完全な公平や平等を望むのではなく、「公平さと不公平さの両面を理解し、どう使いこなすか」という姿勢が、厳しい社会を生き抜く上での鍵になります。
悩んでいるあなたへ
もし今、職場での評価に納得がいかず、心が折れそうになっているなら、一度立ち止まって考えてみてください。
「公平さの中では、自分に改善できる余地がある」
「不公平さの中では、自分が守られている部分もある」
この二つの事実を同時に認識することが大切です。
世の中に完全な公平はありません。逆に完全な不公平でもありません。その狭間の中で、自分にできることを探し、自分の強みを磨き続けること。それが凡人にとって最も現実的で、かつ持続可能なキャリア戦略です。
そして何よりも、自分を追い込みすぎないでください。公平さの残酷さに耐えるためには、冷静に自分を守る心の余裕こそが必要であり、自分の心身の健康こそが全ての仕事と生活の土台となります。
理想の転職を目指すなら
コンサル業界への転職やキャリアアップを目指す場合、エージェント選定も重要な要素の一つです。
未経験者のコンサル転職や、コンサル出身者の経営幹部転職特化など明確な強みがあり、選考対策からキャリア設計まで手厚いサポートがあるエージェントをおすすめしています。
現状に不満や将来に不安がある方は、先ずは以下サイトへの無料登録と無料相談から始めてみるなど、具体的な行動からキャリアプランを探してみてはいかがでしょうか。